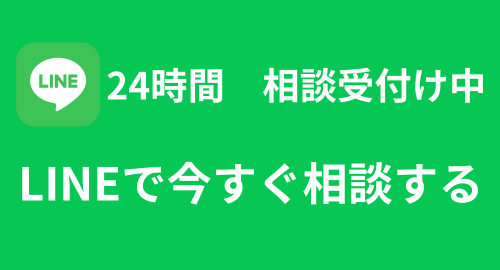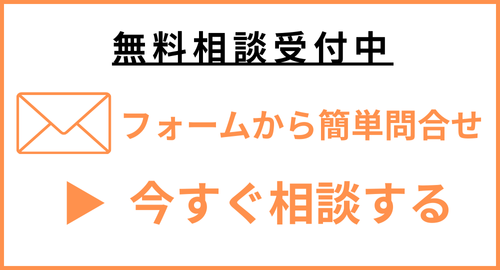相続の手続きはいつまでに? 期限と諸手続きを解説|尼崎 いしの行政書士事務所
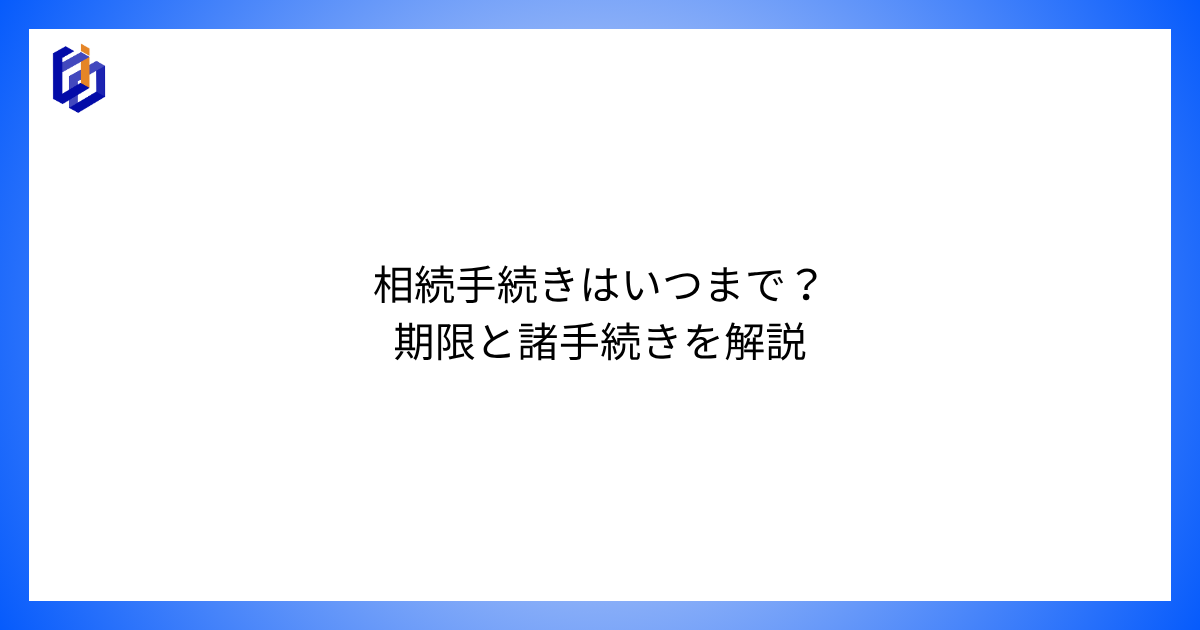
「大切な人を亡くした後、何から手を付ければ良いかわからない…」
相続手続きにはいくつもの期限があり、知らずに進めると不利益やトラブルにつながることもあります。
不安な状態で手続きを進めるのは大変ですよね。
本記事では、相続手続きの全体像や各種手続きの期限、注意点、をわかりやすく解説します。
これから相続手続きを始める方や、手続きの流れ・必要書類・専門家への相談方法を知りたい方に役立つ内容です。
\ 無料で相談する /
相続の期限一覧

相続手続き期限一覧表で全体像を把握しよう
相続手続きは多岐にわたり、それぞれに期限が設けられています。
期限を過ぎると手続きができなくなったり、税金が加算されることもあります。一覧表で全体像を把握しておくと安心です。
以下の表は、主な相続手続きの期限をまとめたものです。
この表を参考に、各手続きを計画的に進めましょう。
| 手続き内容 | 期限 |
|---|---|
| 死亡届・火葬許可申請 | 7日以内 |
| 健康保険・年金の資格喪失届 | 14日以内 |
| 相続放棄・限定承認 | 3ヶ月以内 |
| 準確定申告 | 4ヶ月以内 |
| 相続税の申告・納付 | 10ヶ月以内 |
| 遺留分侵害額請求 | 1年以内 |
死亡後すぐに開始するべき手続き|死亡届・火葬・埋葬料の申請
家族が亡くなった場合、まず最初に行うべきは死亡届の提出です。
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村役場へ提出しなければなりません。
同時に火葬許可申請も必要で、これも7日以内が原則です。
また、健康保険や国民健康保険に加入していた場合は、葬祭費や埋葬料の申請も14日以内に行うとスムーズです。
これらの手続きを怠ると、火葬や埋葬ができなかったり、給付金を受け取れなくなるリスクがあるため、速やかに対応しましょう。
3つの相続方法:「単純承認」「限定承認」「相続放棄」
「単純承認」「相続放棄」「限定承認」のいずれかを、相続があったことを知った日(相続人であることを知った日)の翌日から3か月以内(この期間は「熟慮期間」と呼ばれている)に選択する必要があります。
相続は不動産や預貯金などの「プラスの財産」だけでなく、借金など「マイナスの財産」も引き継ぎます。亡くなられた方の財産の調査を経て、どの方法が最適かをご検討ください。
| 種類 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 単純承認 | プラスの財産もマイナスの財産も含めて相続をします。 特別な意思がないときはこの方法が取られます。 | 「相続放棄」と「限定承認」を選択しなかった場合は単純承認したものとみなされます。 |
| 限定承認 | マイナスの財産を、プラスの財産を限度として支払うことを条件に相続することです。 例1)マイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合 借金:1000万円 預貯金:400万円 手元には相続財産は残りません。しかし400万円を支払うだけで済みます。相続人は自らの財産で被相続人の借金を肩代わりする必要はありません。 例2)マイナスの財産がプラスの財産よりも少ない場合 借金:1000万円 預貯金:1400万円 1000万円を返済した後、手元には400万円が残ります。 | 精算をしないと、プラスかマイナスかどちらになるかわからない場合に有効な手続きです。 限定承認は、相続人全員が共同して家庭裁判所に限定承認する旨を申し立てる必要があります。手続きの複雑さから利用される機会は少ないようです。 |
| 相続放棄 | プラスの財産もマイナスの財産も含めて相続を放棄するものです。 マイナスの財産が明らかに多いとき、相続争いに巻き込まれたくないときなどに有効です。熟慮期間の間に家庭裁判所に相続放棄をする旨を申し立てます。 | 故人の財産に一度でも手をつけてしまうと「相続の意思があった」とみなされ、相続放棄が認められない場合があります。相続放棄をする可能性がある方は記憶に留めておいてください。 |
相続発生から進める遺産分割協議や調査の流れ
死亡届などの初期手続きが終わったら、次は相続人の調査や遺産分割協議に進みます。
まず戸籍謄本などを取り寄せて法定相続人を確定し、相続財産の調査を行います。
相続人が確定し、遺産がまとまれば遺産分割協議に進みます。
遺産分割協議自体には法的な期限はありません。しかし、相続税が発生する場合は10ヶ月以内に申告・納税の必要があります。また、手続きに時間をかけ過ぎると、相続人が死亡して代襲相続が発生(相続人の子などが相続人になる)するなど事態が複雑になりかねません。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てたり、弁護士費用が必要になったりなど、さらに時間や費用がかかる恐れがあります。
できるだけ揉めないように遺産分割を済ませたいところです。
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。
相続人全員が遺産分割協議書に署名・押印(実印)し、印鑑証明書を添付します。
弊所は「相続人の調査」「相続財産の調査」「遺産分割協議書の作成」をお手伝いできます。
お気軽にお声がけください。
\ 無料で相談する /
その他の手続き
行政書士は業務として受けられない「税関係」「登記関係」の一般的な知識を説明します。
・ 不動産登記
令和6年4月1日から「不動産の相続登記」が義務化されました。
親族が亡くなって相続した不動産を、相続登記しない状態が長く続いてきました。所有者がわからない不動産が増え、倒壊の危険性や犯罪に使用されるリスクを抱えた「空き家問題」が社会の課題となっています。
不動産登記は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。正当な理由なくこの義務を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
不動産の名義が亡くなった方のままだと、売却や担保設定などができません。また財産の活用や処分が困難になるだけでなく、時間が経つほど相続人が増え、話し合いが難しくなります。速やかに手続きを済ませましょう。
不動産登記の代行ができるのは司法書士(または弁護士)のみです。弊所では登記ができません。
不動産登記でお困りの場合は、信頼できるの司法書士を紹介できます。お気軽にご相談ください。
・所得税の準確定申告
被相続人が亡くなった日(相続の開始があったことを知った日)の翌日から4か月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告・納税する必要があります。
亡くなった方が確定申告をする前に亡くなった場合、その年の1月1日から亡くなった日までの所得を、相続人が申告と納税を行う手続きです。
・相続税の申告・納税
相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告・納税する必要があります。
相続や遺贈によって取得した財産の価額の合計額が「遺産に係る基礎控除額」(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に課税対象となります。
税に関する相談や手続きは税理士しか受けられません。
弊所は「相続専門の税理士」との共同事務所です。
節税や生前贈与などの対策を知りたい方は、税理士を紹介させていただきます。
\ 税理士紹介可能 /
困ったら行政書士などの専門家へ相談を
相続手続きでは、親族間の意見の食い違いや財産分割をめぐるトラブルが発生しやすいです。
トラブルを防ぐためには、早めに相続人全員で話し合いを行い、遺産分割協議書を作成することが大切です。
また、複雑なケースや意見がまとまらない場合は、士業をはじめとする専門家に相談することで、公平かつ円滑な解決が期待できます。
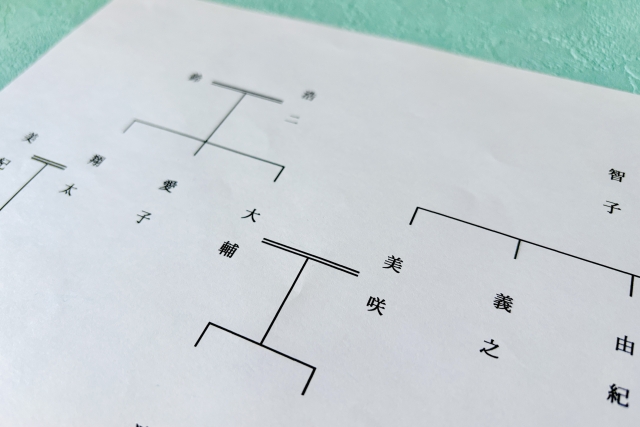
行政書士ができること
| 支援できる手続き | 内容 |
|---|---|
| 相続人調査・相続関係説明図の作成 | 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を収集し、「誰が相続人であるか」を特定します。その結果を相続関係説明図に記載します。 |
| 相続財産調査・財産目録の作成 | 被相続人が所有していた不動産や預貯金、負債などの財産を調査し、財産目録の作成をサポートします。 |
| 遺産分割協議書の作成支援 | 相続人全員での遺産分割協議がまとまった際に、その内容を法的に有効な書面として作成します。 |
| 遺産承継業務 | 相続人全員の代理人として、預金の解約などを代行することも可能です。 ただし、遺産分割の調整で一方の利害に立つと非弁行為となるため、法定相続分での分配が前提となります(合意が形成されている場合は、法定相続分ではない代理行為も可能です)。 |
| 各種書類作成、届出、手続き支援 | 年金、健康保険、事業の許可の変更手続きなど、多岐にわたる相続関連の届出や手続きの書類作成を支援します。 |
他士業との連携
相続税申告が必要な場合の税理士への、不動産登記が必要な場合の司法書士への橋渡しなどが可能です。各専門分野の士業と連携し、相続手続き全般を円滑に進めるためのコーディネートを行います。
司法書士: 不動産の相続登記に関する相談など。
税理士: 相続税の計算や申告、節税など税務相談、生前贈与に関するアドバイスなど。
弁護士: 相続人同士の紛争解決や遺言に関するトラブル、成年後見人選任の申し立てなど。
さいごに
相続は「争続」ともなりかねません。早めに専門家に相談し、適切な手続きを進めること。
そのことがご自身や大切な家族の安心に繋がります。
行政書士は相続手続きの入り口としてお悩みをお聞きします。
初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。
\ 無料で相談する /